ドキュメンタリー映画『ダゲール街の人々』を観る。
どうも、週末翻訳家です。
プライムビデオでおすすめに上がってきていた『ダゲール街の人々』アニエス・ヴァルダ監督を観ました。
フランスはパリ14区、モンパルナスの一角にあるダゲール通りに集う人々の暮らしを切り取った、淡々としたドキュメンタリー映画です。
制作年は私が生まれたころ。
今となってはそうとう古めかしい映像でびっくりしますが、うちの父が当時一生懸命撮ってくれた8ミリフィルムのセピア色の映像を思い出し、なつかしい気持ちになります。
面白いストーリーがあるわけでも、事件があるわけでも、ことさらユニークな人が出てくるわけでもありません。
退屈して途中で観るのをやめてしまうかもと思いながら観はじめたのですがまったく杞憂でした。
つきつめると映画っていうのは、人間が生きて動いているだけで面白いものなのだな。
そんなことを思いました。
あの時代(日本で言うと昭和後期)のおおらかさには、びっくりしたり、うらやましく思ったり。
小さな個人店舗がいくつか出てくるのですが、ついつい「この品物はいつからあるのか?消費期限とか大丈夫なのか?」ということばっかり心配して観てしまいました。
再利用のくすんだ化粧瓶、パンの手づかみ、お肉を切ったままの素手でおつりの受け渡しなどなど・・・
いまの衛生観念からすると、「!!???」となりますが、私が生まれた時代ってこんな感じだったんだなって。
かぶれたり、お腹壊したら壊したで、それもまた人生。
かといって今より人間が軽んじられていたかというと、そうでもないような気がするんです。
香水店のご夫婦がとても印象的でした。
妻の方は今でいう認知症なのかもしれません。
いつも悲しげな表情で、店の外を眺めています。
この時代には病名すらなかったのかも。
夕方になると妻が外に出て行きたくなるのは、彼女の中の何かがそう訴えるから。
夫はそう言って、ありのままを受け入れます。
ただ1日1日があるようにあるだけの人々の暮らし。
こんなふうに人間があるがまま生きて死ぬことができる場所は、今あるのでしょうかね。
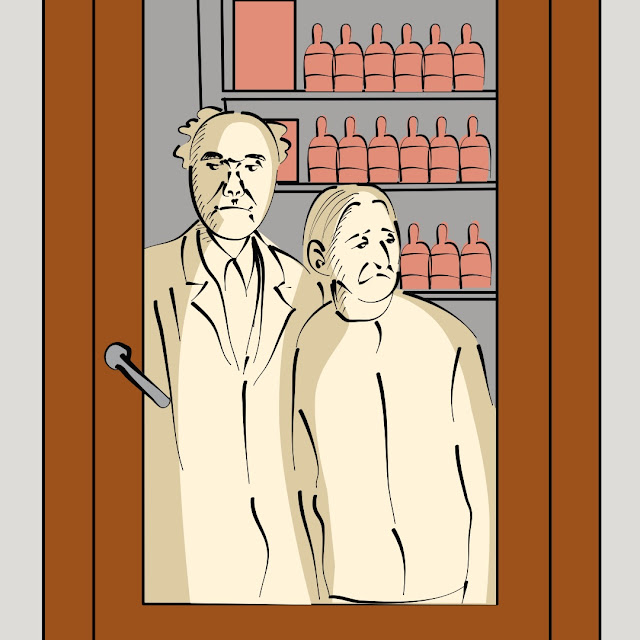

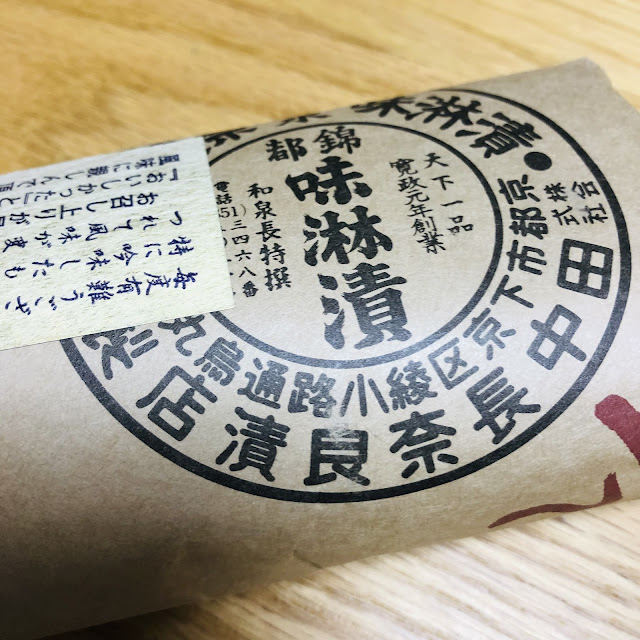
コメント
コメントを投稿